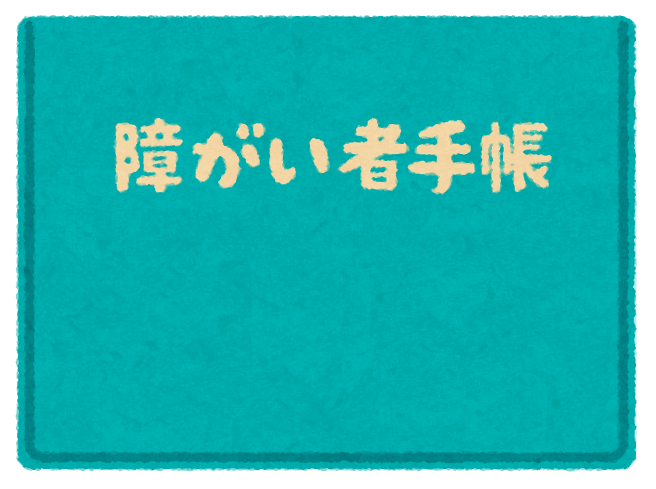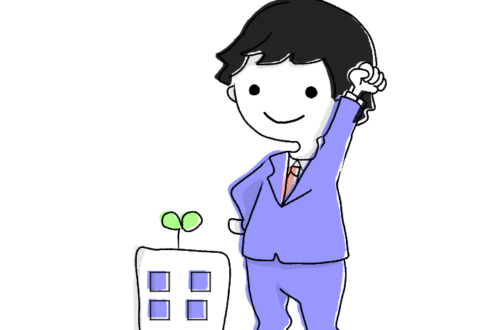児童養護施設とは
児童養護施設とは
諸事情により保護者がいない子どもたちや、虐待などにより親元を離れざるを得なかった子などを養護し、安心して生活できる場を提供し成長をサポートする児童福祉施設です。
以前は、「孤児院」と呼ばれていましたが、1947年~1997年にかけて名称を変え、
「児童養護施設」と呼ばれるようになりました。

対象年齢は、2歳頃~原則18歳までですが、例外的に、2歳未満の乳児や、成人後も20歳までの利用をしている人もいます。
退所までの期間が決まっているため、健やかな成長を見守るとともに、自立した生活ができるように、適切な学習指導や生活指導を行う必要があります。

~生活の場を提供する施設による連携~
◎乳児院
保護者による養育が困難になってしまった場合、2歳未満の乳児は基本的に「乳児院」を利用します。
ただし、児童相談所の判断で乳児が児童養護施設を利用する場合もあります。
例えば、兄弟で同時に入所する場合。
兄弟分離を回避するという観点から、同じ児童養護施設に入所することがあります。
◎成人後
子どもが18歳になると、原則施設を退所します。
ただし、子どもたち自身が退所のタイミングで、自立して生活の場を確保できない際、20歳まで継続して児童養護施設を利用することがあります。
施設職員は、子どもたちの自立のために就職や生活面での困りごとに対応する必要があります。
また、心身の障害が伴い、就職や自立が難しい場合には、グループホームなどの利用も考慮しなければなりません。

解説ちゃん:
以前働いていたスタッフから聞いたことがあるんだけど、18歳になり就活にも成功して、スムーズに退所する運びになった男の子。自身の力で生活しようと頑張っていたけれど、いざ新生活が始まると、トラブルが起きてしまったり仕事が続かなかったりしたんだって。結局2か月後に、児童養護施設に戻ってくることになったそうだよ。退所した子どもたちの状況を把握するのも大切なんだね・・・。
施設の形態としては、「大舎制」「中舎制」「小舎制」などがあります。
以前は、ほとんどの施設が「大舎制」での対応をしており、20人以上の子どもたちが同じ建物で生活をしていました。この形態では、男女や年齢別などで部屋分けをしていますが、食堂・お風呂・トイレなどの設備を共同で使用します。いわゆる、寮のような形で運営をしています。
近年では、より家庭に近い形で生活することが望ましいとの考え方から、小規模化が進んでいます。
「小舎制」では、施設の敷地内の家屋で生活します。入所の子どもも12人以下と、「大舎制」に比べると少人数での生活となりますので、スタッフとも密にコミュニケーションが取りやすくなるメリットがあります。
また最近では、児童養護施設の分園として、地域の一般住宅で生活する「グループホーム」も増えてきました。

解説ちゃん:
大舎制・小舎制、どちらも運営している施設もあります。
近年の小規模化のために、建物の建て替え等が完了しておらず移行中のため、大舎制で生活する子と小舎制で生活する子に分かれてしまっている所もありますね。
生活の場所が分かれるということは、人員もより必要になります。児童養護施設では、人手不足も大きな問題です。

児童養護施設では、虐待経験のある子どもが53.4%と半数以上が苦い想いを抱えています。
親御さんの状態によっては、入所秘密の児童もいます。
個々人のプライバシーを尊重し、学校や地域との連携も大変重要となります。
職員は児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員などが配置されています。
業務は児童には孤立した子がほとんどですので、心のケアや食事・入浴・掃除等の生活支援、18歳になると退所=自立になりますので、自立に向けた支援、就労相談等を行います。
勤務は早出・日勤・遅出・夜勤など不規則勤務です。
※後日、業務内容やスタッフとして働くために必要な資格、お給料面についてより詳しく追記いたします。
広告
(2021.01 投稿)
(2025.06 追記)